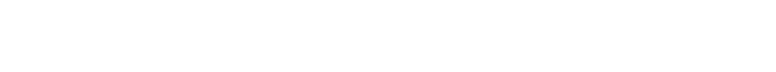分子認識材料・超分子デバイス研究会とは
分子認識化学は1967年にクラウンエーテルが発見されて以降、極めて高いレベルでの学術的深化を続けてきました。それは2度にわたってノーベル化学賞が本分野に授与されたことからも窺い知れます。しかし、分子認識化学を基軸とする技術の社会普及は未だ達成されていません。これは、デバイスなどの実使用を見据えた研究開発が行われていないことに起因します。他方、グルコースセンサなどに使われる生体由来の分子認識材料は一部実用化されていますが、化学的・熱的不安定性の問題があり、日常生活において幅広く使われているとは言い難いのが現状です。この課題を解決するため、本研究会では、分子レベルでの材料設計・開発とそれに続くデバイス応用を包括的に研究し、ひいては社会実装の迅速化を目指します。実用化には分野横断的な議論が不可欠であるため、化学・機械・電機・情報・環境・医療・食品・商社・アートなどの異分野から広く参加者を募り、分子認識材料の基礎・実践応用に関して多角的に議論します。学理探求(水源)から各メーカー(川上)、マーケティング・販路(川下)までを見据えたシーズ・ニーズオリエンテッドの双方向の視点で分子認識材料・超分子デバイスの水脈(技術戦略)を探すことが目的です。
代表挨拶

東京大学生産技術研究所 |
身の回りに溢れる化学情報を可視化する技術開発の重要性は,猛威を振うウイルスのみならず,身の回りに溢れる目には見えない様々な化学情報を可視化するセンサを具現化することで,安心・安全の社会が実現されます。本研究会では,そんな社会の第一歩に向けて,どこでも・だれでも・いつでも測れる化学センサの実現を目指し,分子スケールからデバイスに及ぶスケール横断型研究を展開します。 |